育休中に扶養に入ったほうがいいって聞いたことあるけど、どういうこと?
私は該当するの??扶養って難しそう・・・そんなお悩みをお持ちのみなさん📣
こんにちは、2024年10月から育休に入っている1児のママです😀
育休中に「扶養ってどうなるの?」とモヤモヤしていたので、自分で調べてまとめてみました。
結論、育休ママは税法上の扶養に入れば、OK!!!
「扶養に入る」は2種類ある!税金と社会保険の違いをチェック
「育休中は夫の扶養に入ったよ」と先輩ママに聞いて、「自分もそうした方がいいのかな?」と悩んだことはありませんか?
実は、“扶養に入る”といっても、次の2つのパターンがあるんです。
- 社会保険上の扶養
- 税法上の扶養
この2つは、対象となる制度も、手続きも、影響も違います。
まずはこの違いをしっかり知っておくことが大事です!
社会保険上の扶養とは?
ここでは、奥さんが育休中で、会社員の旦那さんの扶養に入るケースを例にして説明します。
社会保険の扶養に入ると、保険料の支払いが不要になる
社会保険の扶養に入れる条件は、「扶養に入る人(=奥さん)の年間収入が130万円未満であること」。
この条件を満たすと、奥さんは自分で健康保険料や年金保険料を支払わなくても、旦那さんの社会保険に加入できるようになります。
つまり、育休中で収入が少ない場合、扶養に入ることで社会保険料の負担をゼロにすることができるのです。
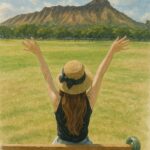
育休中に扶養に入ると、奥さんの社会保険料がかからなくなるってことだね!だけど・・・
育休中は「社会保険の扶養に入らなくていい人」がほとんど
「育休中は収入が減るから、夫の扶養に入れるのでは?」と思う方も多いですよね。
でも実は、育休中であっても、会社に在籍している限り、社会保険の加入資格は継続されます。
さらに、育児休業の開始月から終了の前月までの間は、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが「免除」される仕組みがあります。
つまり、育休中のママは自分の会社の社会保険にそのまま加入しつづけ、保険料も払わなくていいため、わざわざ夫の社会保険の扶養に入る必要はないケースがほとんどなんです。
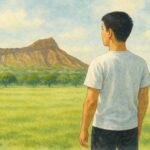
えっ じゃあ、育休中は社会保険料払わなくていいの?
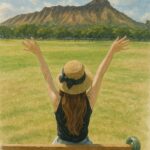
そう!会社に在籍したままなら自分の保険に入ったままで大丈夫なんだよ♪、
税法上の扶養って?
ここでも、奥さんが育休中で、旦那さんの扶養に入るケースを例にして説明します。
税法上の扶養に入ると、旦那さんが払う税金が少なくなる
育休中であっても、1月〜12月の年間の給与収入が103万円以下であれば「配偶者控除」が適用され、旦那さんの所得税や住民税の負担が軽くなります。
また、収入が103万円を超えても、201万円以下であれば「配偶者特別控除」の対象となり、段階的に控除額が減少しながらも税金の軽減を受けることができます。
このように、税法上の扶養に入ることで、旦那さんの税金が安くなる可能性があるんです。
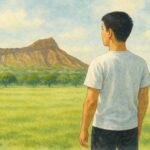
奥さんが育休中で収入が減れば、税法上の扶養に入って、旦那さんの税金が安くなるってことか!
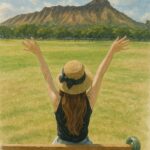
そう!例えば、年の途中から育休手当を受給し、今年は収入あったから・・・という人は配偶者特別控除の対象になるかもしれないね
育休中は、税法上の扶養に入るほうがいい人が多い
前述の「給与所得」の計算には、育児休業給付金(育休手当)は含まれません。
そのため、1年の途中から育休に入って収入が大きく減るママは、年間の給与収入が103万円以下となり、配偶者控除の対象になるケースが多いです。
該当する場合、年末調整で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の申告をするだけでOK。会社員であれば、夫の勤務先での年末調整で申告できます。
所得税や住民税の負担が減るので、申告を忘れずにしておきましょう♪
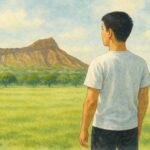
手続きもかんたんだし、扶養に入れるならやっておいたほうがいいね!
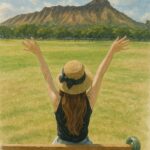
ちなみに奥さんが復帰して要件を満たさなくなったら、年末調整で申告しないだけでOKだよ!
税法上の扶養に入るメリット①|所得税・住民税が減る!
配偶者控除や配偶者特別控除は、「所得控除」に含まれます。
この控除があることで、旦那さんの所得税・住民税が安くなります。
税金のしくみは少しややこしいですが、ざっくりとした計算式は以下の通りです:
- 年収 − 給与所得控除 = 所得
- 所得 − 所得控除(配偶者控除など)= 課税所得
- 課税所得 × 税率 − 税額控除 = 所得税
住民税も同様に、課税所得が減ることで税額が下がります。
| 年収の目安(給与) | 課税所得額(概算) | 所得税率 | 所得税控除額(38万円控除適用時の減税額見込み) | 住民税控除額(33万円控除) | 所得税+住民税合計の税軽減額(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 約280万円 | 約1,800,000円 | 5% | 約19,000円 | 約33,000円 | 約52,000円 |
| 約350万円 | 約2,500,000円 | 10% | 約38,000円 | 約33,000円 | 約71,000円 |
| 約500万円 | 約4,000,000円 | 20% | 約76,000円 | 約33,000円 | 約109,000円 |
| 約750万円 | 約6,500,000円 | 20% | 約76,000円 | 約33,000円 | 約109,000円 |
| 約800万円 | 約6,900,000円 | 23% | 約87,400円 | 約33,000円 | 約120,400円 |
| 約900万円 | 約8,000,000円 | 23% | 約87,400円 | 約33,000円 | 約120,400円 |
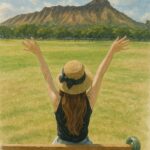
たとえば年収500万円だった場合、配偶者控除があると
所得税は約7.6万円、住民税は約3.3万円安くなるよ!
※その他の控除状況などにより変動します
税法上の扶養に入るメリット②|保育料が安くなる!
保育料は、原則として「父母の住民税所得割額(=市町村民税の一部)」を合算した金額をもとに決定されます。
この住民税所得割額は、課税所得に一定の税率をかけた金額のこと。
つまり、配偶者控除を受けると課税所得が減る → 結果的に住民税所得割額も減る → 保育料が安くなるという流れになります。
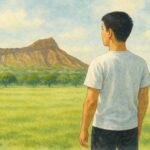
税金が減るだけじゃなくて、保育料にも影響があるんだね!
ただし、保育料が実際に安くなるのは、控除を受けた「翌年の9月から」が一般的です。
住民税は毎年6月に新年度分が決まり、そのデータをもとに各自治体で保育料の見直しが行われるため、
実際の保育料の変更反映は9月からになる自治体が多いです。
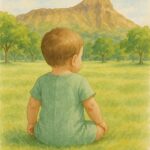
2025年に育休&扶養に入ったら、保育料が下がるのは2026年9月からってことだね!
*詳しい見直しタイミングは自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体に確認するのがおすすめです
わが家の場合|育休中の扶養はこう考えました
扶養に入るかどうか悩んだ、わが家のケースをご紹介しますね。
私は2024年10月から育休に入りました。1月〜9月までは収入があったため、
2024年の扶養条件は満たせず、扶養には入っていません。
ただ、2025年は育休手当のみとなるため、税法上の扶養に入る予定です。
保育料については、2025年9月以降に見直され、安くなるのではと予想しています!
まとめ|育休中の扶養、どうするのが正解?
育休中の「扶養」ってひとことで言っても、実は2種類あるんです。
- 社会保険上の扶養(保険料が免除になるかどうか)
- 税法上の扶養(税金や保育料に関係)

このうち、育休中にチェックすべきなのは税法上の扶養のほう!
なぜかというと…
- 育休手当は「給与所得」に含まれない
- だから配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる人が多い
- 結果、旦那さんの税金が減ったり、保育料が下がったりする可能性あり!
ちなみに、社会保険の扶養は「育休中でも会社に在籍していれば保険料が免除される」仕組みがあるから、わざわざ扶養に入らなくてもOKなことが多いです◎
我が家も、2025年からは税法上の扶養に入る予定です!
自分がどっちの扶養に関係するのか、よかったらこの記事を見ながらチェックしてみてくださいね☺️
\育休中にオススメの家計管理記事/
👉️【年間2万円の節約】営業電話がない自動車保険一括見積りサイトを使ってみた話
\育休中の制度解説記事/




コメント